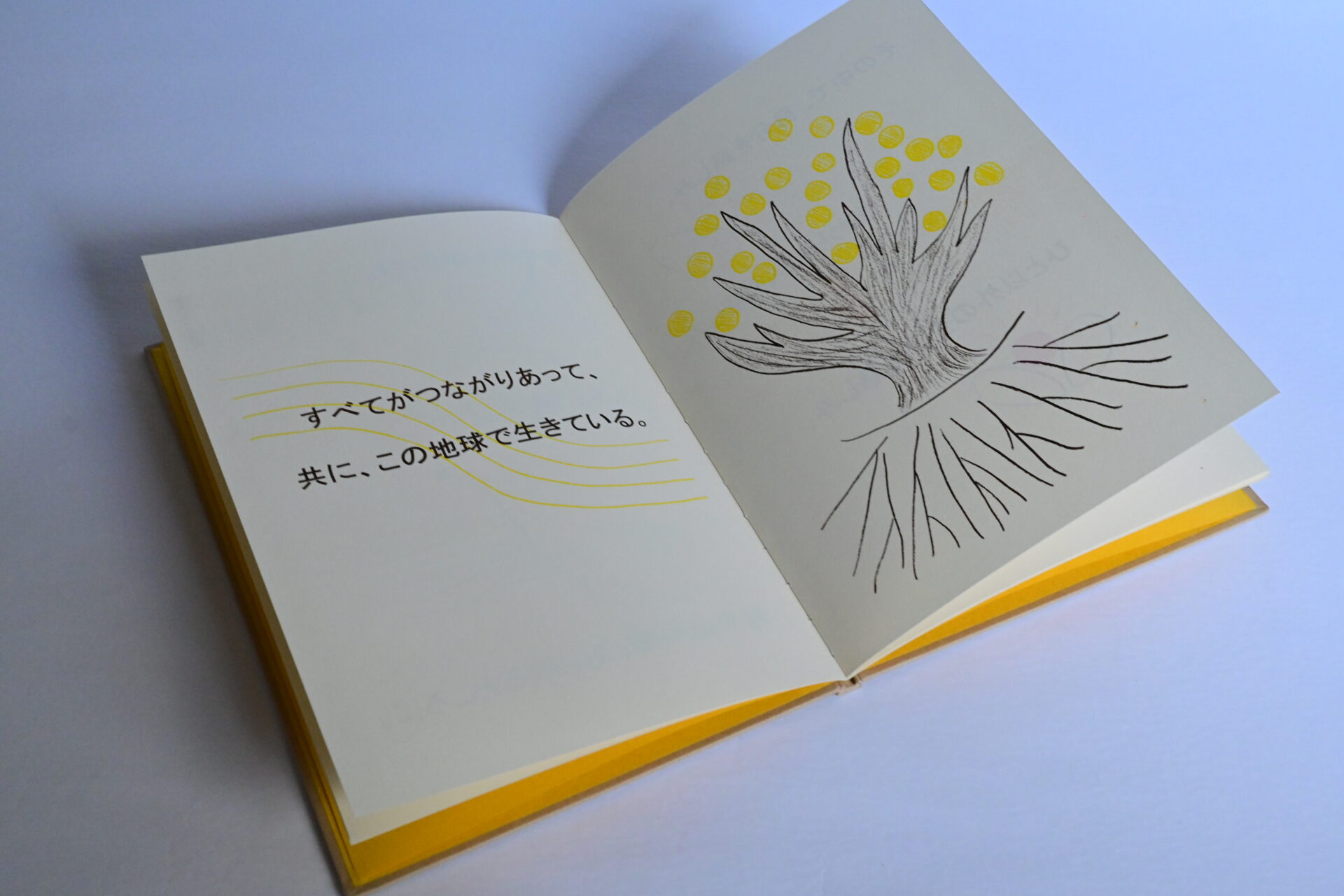【てならい後記】曲げて伸ばせる錫(すず)の器、すずがみ作り 鍛金ワークショップ
こんにちは!てならい堂スタッフのひかるです。
シマタニ昇龍さんの「すずがみ」ワークショップのレポートになります!
そもそも「すずがみ」って何だろう??と皆さん思われるのではないでしょうか?
「すずがみ」とは錫(すず)を素材とした板状の製品です。「紙のように薄い錫(すず)」という特徴から名前が付けられました。錫は柔らかい勤続なので、全く力を入れなくても曲げられるんです!
用途やシーンに合わせて自由自在に使え、一度形を変えても綿棒のような道具を使って伸ばすと簡単に元の平らな状態に戻すことができて便利(^^)/
今回はそんな「すずがみ」を叩いて補強しながら、そこに柄を付けていくワークショップになります!
皆さんに参加理由を伺うと「技術が凄いなと思っていた。体験したいと思っていた」「金属を打つ時間。集中する時間を体験したいと思っていた」「色々な体験をやってきたが、金属の体験はしたことが無かったなと思って体験したいと思っていた」など、様々な思いをお持ちでした。
ワークショップの冒頭、島谷さんは昇龍で「おりん」を作り続けてきた中で、その技術を他の用途にも活かせる方法を模索したいと思い、日常使いもできる「すずがみ」の制作を始めたとお話しされていました。

作り方はシンプル。無地の「すずがみ」を柄が付いた金槌で叩き、模様を付けていきます。元々冷たい印象を受ける金属ですが、模様を付けることにより、手仕事のぬくもりが生まれます。今回は“風花(かざはな)”と“五月雨(さみだれ)”という2種類の槌目で模様を付けていきます。

両方とも日本の美しい気象現象に見立てて柄や名前を付けていて、“風花”とは雲の少ない晴れた日に舞う雪で、その雪が積もった様な柄。“五月雨”とは五月に降る長雨。その粒を打ち付けたような模様です。素敵ですね・・・!!
作り方はシンプル…とは言いつつ、まずは金槌で叩くのが思っている以上に大変!!普段、金槌の慣れない重さに加え、叩き続けるのは力と根気が必要です。

また、模様を付けるだけでなく、万遍なく「すずがみ」全体を叩くことも重要。昇龍さんの「すずがみ」は純度100%の錫を使用しています。(通常は取り扱いやすさや加工性を高める為に錫100%に対して1%の銀や銅を入れて硬くすることが多い。)
何度も金槌で叩くことで、曲げ伸ばしによる劣化が軽減されて、何度も曲げて使用することができるようになります。

皆さん2種類の模様を使って、色々アレンジをしています。見ているのも楽しい。人によっては風花と五月雨を半々にしたり、富士山の形にしたり、作品に個性が出ていました!

「すずがみ」はお皿にも、箸置きにも花瓶にも…使う人の発想次第で様々なバリエーションが生まれます。しかも、食洗器もOKで、且つさびないという点もありがたいです!
島谷さんはキャンプのお皿として愛用されているそうです。コンパクトですし、洗うのも楽で便利ですよね。「すずがみ」はてならい堂の店舗でも商品の取り扱いをしているので、ぜひお店にお越しの際は実際に手に取ってご覧ください。